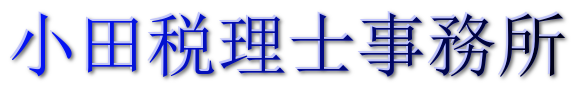社会保険の不思議 その2

【医療保険はいくつ?】
年金に続き、医療保険の不思議を考えてみましょう。
日本は公的制度による国民皆保険です。
制度も1つという感じですが? そうではありません。
協会けんぽ、組合健保、国保、惜しいですね。まだまだあります。
具体的には、
協会けんぽ(1団体) 約4100万人、組合健保(1388団体) 約2800万人、
市町村国保(1716団体) 約3000万人、共済組合(85団体) 約800万人、
後期高齢者医療(47団体) 約1800万人、船員保険、国保組合もあります。
団体数は約3400団体です。ものすごい数の医療保険の団体があります。
何故そうなったのかと言えば、
戦前(大正)から国民皆保険となる昭和36年迄の歴史の積み重ねでしょうね。
もっとも、窓口負担は統一されています。
75才以上が1~3割、70以上が2~3割、6才未満が2割、後は3割です。
しかし、団体によって付加給付が異なっています。
例えば協会けんぽ、インフルエンザの予防接種は×です。組合健保は○とかです。
【保険料負担は?】
次に保険料、財源を見てみましょう。
協会けんぽ、
公費が約16%、残りは保険料 約10%(労使折半)、
年金と同様に所得の上限(月139万円、賞与573万円)があり、扶養家族は負担なしです。
組合健保、
保険料 約9%(労使折半)、扶養家族は負担なしです。
保険料率、所得上限や会社が余分に負担するかどうかは団体毎に異なります。
共済組合も同様です。
市町村国保、団体数は多いですが、運営は県単位、実務は市町村です。
公費は50%、残りは保険料です。
この保険料、協会けんぽ、組合健保、共済組合の月給+賞与の保険料ではなく、
所得割(収入)、資産割、均等割、平等割により決まります。
扶養家族も負担なしではなく、保険料が生じます。
もっとも保険料の世帯上限は85万円(介護保険は除く)です。
後期高齢者医療、
公費が50%、他の医療保険団体からの支援金が40%、保険料は10%です。
保険料は個人単位、所得割と均等割により決まります。上限は66万円です。
頭が痛くなります。
窓口負担は統一なのですが、公費の割合、所得や保険料の上限はバラバラです。
団体毎に保険料の決め方や保険料率も異なります。
従業員が負担する保険料が約5%ではなく2%台の団体もあります。
後期高齢者医療の他団体からの支援金と保険料も考えさせられます。
医療保険、年金以上に不思議の累乗です!!